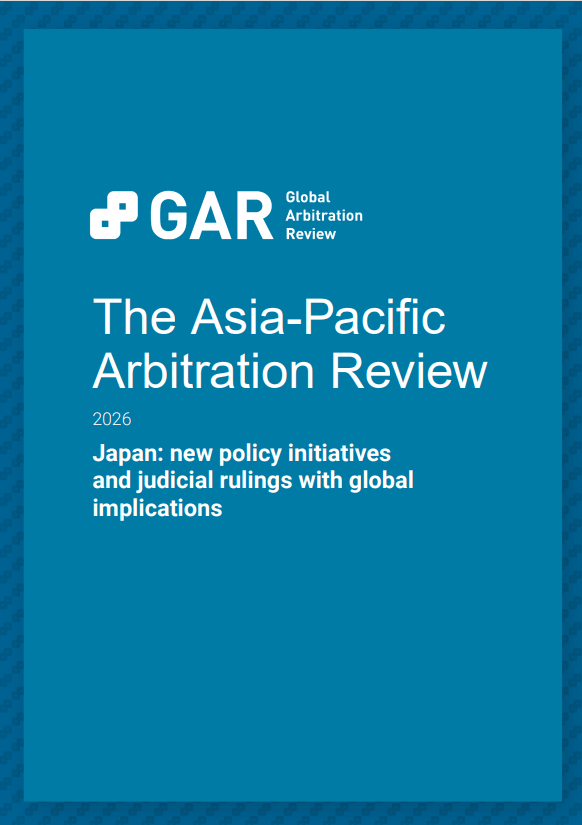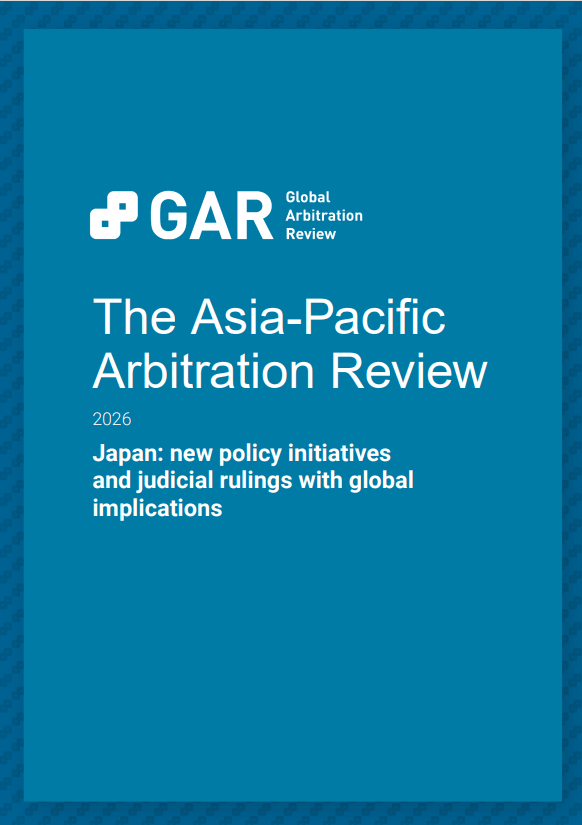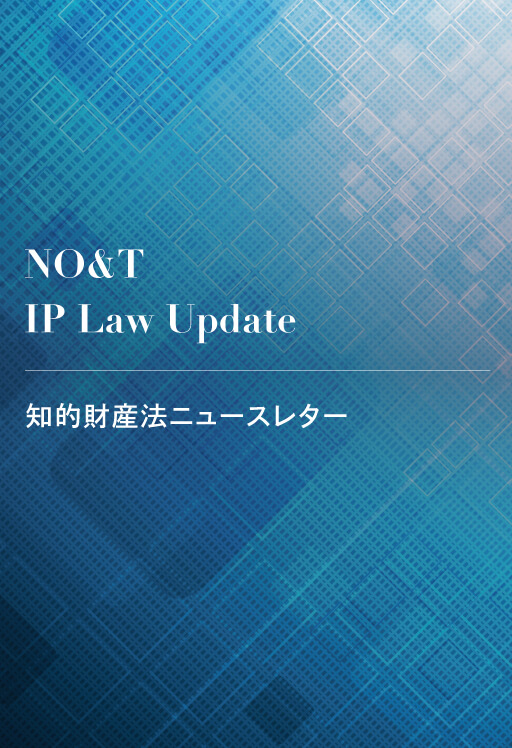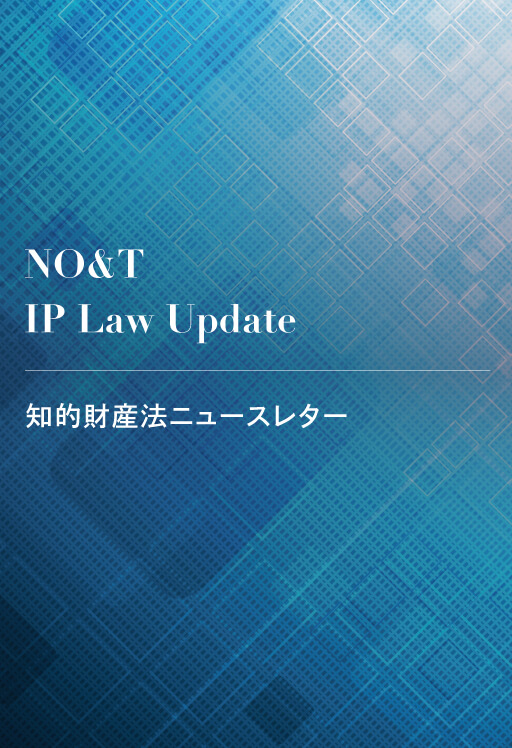はじめに
9月30日月曜日の日本経済新聞朝刊の法税務面に、「国税当局 折れた『宝刀』 非上場の相続株式 価格評価で敗訴」との記事※1が掲載されております。当職のコメントも併せて掲載いただいております。どうぞご覧くだされば幸いです。
同記事において、相続税の財産評価について、いわゆる「総則6項」の適用を否定する旨の高裁判決が本年8月に出されたことにつき触れられています。この判決は、東京高裁令和6年8月28日判決※2(「本判決」)です。本判決は、国が上告受理申立てをしなかったため、確定しています。本判決は、一審の東京地裁令和6年1月18日判決※3(「一審判決」)を是認したものであり、総則6項の適用を肯定した最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(「別件最判」)の後に、総則6項の適用を否定したはじめての判決といえます。
一審判決については、当職の本年2月のニュースレターにおいて、簡単に解説をしました。今回は、その控訴審判決である本判決について、同ニュースレターをアップデートする形で、本判決とその意義等、とりわけ「総則6項」の適用の限界がどこにあるのか、今後の実務はどうなるのかにつき、ごくごくカジュアル、インフォーマルかつ簡潔にではありますが、解説いたします。
本判決の事案
本判決の事案は、以下のようなものです。
-
相続税の申告における財産評価につき、総則6項を適用して、財産評価基本通達による評価を否認して、いわゆる時価で評価をして増額更正処分がされた事案です。
-
総則6項が適用された相続財産は、被相続人Aが保有していた非上場会社X社の株式です。別件最判におけるような不動産ではありません。
-
財産評価基本通達の定めにより、つまり総則6項を適用しないで、X社株式を評価したときの評価額は、1株当たり8186円です。X社の場合はその株式の評価方法は類似業種比準価額方式となります。
-
被相続人Aは、X社の大株主・代表取締役であり、X社のカリスマ的なオーナーでした。
-
被相続人Aは、平成26年初めから、自ら及び親族の保有するX社株式100%を、第三者たるY社に売却するM&Aの準備や交渉を行っていました。
-
その中で、平成26年5月29日に、被相続人AとY社との間で、X社株式100%を1株当たり10万5068円で売却するとの内容で、同売却に向けて協議を行う旨の基本合意(法的拘束力なし)がなされました。
-
しかし、被相続人Aは、平成26年6月11日に死亡し、本件相続が開始しました。
-
その後、被相続人AからX社株式を相続した相続人ほかが、Y社と最終契約を締結の上、平成26年7月14日に、X社株式100%を、実際にY社に対し1株当たり10万5068円で売却しました。
-
Aの相続人は、X社株式につき、上記のとおり類似業種比準価額方式による評価額である1株当たり8186円と評価して相続税の申告をしました。これに対し、課税庁は、この8186円は上記の10万5068円の約10分の1にすぎないなどとして、総則6項を適用し、X社株式の評価を1株当たり8万373円(課税庁が別途取得した株式評価額)として増額更正処分をしました。
本判決の判示
本判決の判示は、以下のようなものです。
-
別件最判の判断枠組みからすれば、本件において、租税法上の一般原則である平等原則の観点から、「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある」といえるか否かが問題となる。
-
別件最判は、総則6項の運用の有無に当たり、その件の被相続人が相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮している。しかし、本件ではX社株式の評価額を下げるような行為がされたことは窺われず、本件の被相続人A及びAの相続人によるそれに類する行為があったとは認め難い。そうである以上、被相続人A及びAの相続人の行為に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はない。
-
取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的な評価を経ない限り判明し得ないものであって、とりわけM&Aが行われる場合においては、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない。類似業種比準価額方式による評価額である8186円が上記の10万5068円と大きく乖離しているからといって、更正処分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格である1株10万5068円が交換価値を反映したものであるとして、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情が存在していたということにはならない。
-
総則6項の適用に当たり、上記乖離の有無を公平に判断するためには、他の相続案件も含め、取引相場のない株式その他市場性のない相続財産の全てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的な理由がないのに、特定の相続財産のみについて専門的評価を行い、これを基にして課税処分を行うことは、平等原則に反するものというべきである。
-
売買契約の成立後に相続が開始した場合であれば、売主の相続財産は売買代金債権になり、その価額は原則として売買代金額で評価されるところ、本件の相続開始は売買契約の成立前であるし、Aの相続人とY社との間でX社株式の売買契約が成立し、1株10万5068円による売買代金債権に転化する蓋然性が高かったと認めることもできない。そもそもそのような蓋然性の程度を基準にすることは適切でない。
-
国は、総則6項の適用に当たり、租税回避行為があることは要件とはならないと主張するが、当裁判所はそのような要件が存するものと説示しているものではない。
-
したがって、X社株式の1株当たりの価額については通達評価額(8186円)によって評価すべきであり、総則6項を適用して8万373円を用いてX社株式を評価した増額更正処分は、別件最判の示した枠組みに照らし、平等原則という観点から違法である。
本判決の意義等
本判決の意義等としては、以下の点を指摘することができると思われます。
-
本判決の事案においては、判示もいうように、租税回避的な要素はありません。要は、非上場会社X社のカリスマ的なオーナーである被相続人Aが、売主側で、買主候補であるY社とごく真っ当なM&Aの交渉をしていたところ、単にその中途で亡くなったというだけです。その意味では、本件はいわゆる「筋のよい」事案であるといえ、その結論自体は首肯できるものです。
-
それでも課税庁が「けしからん」と考えた理由は、相続開始前に基本合意により事実上ではあるが了解された(かつ相続開始後に実際に最終契約で合意され決済された)1株当たり10万5068円という価格と、類似業種比準価額方式による評価額である1株当たり8186円の間には、約10倍の差(乖離)があるという点であると思われます。併せて、仮に被相続人Aが存命中にM&Aの最終契約の締結又は決済がなされていたとしたならば、1株当たり10万5068円の売却代金が未収金又は現金としてAの相続財産となっていたとの点も理由の1つであろうと思われます。
-
しかし、先の別件最判の最も重要な判示は、「本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない」との点にあったといえます(当職の2022年4月のニュースレター参照)。これは、調査官解説によれば、「同様のかい離は類似の不動産にも広く存在し得る以上、これを相続する潜在的な他の納税者と同じく通達評価額によったとしても租税負担の均衡が害されることはなく、むしろ、当該納税者についてのみ通達評価額を上回る価額によることは不合理というべきである(このようなかい離は、本来、評価通達の見直し等によって解消されるべきものといえる。)。」ということです(当職の2022年12月のニュースレター参照)。
-
すなわち、別件最判の射程を検討するに当たっては、問題視されている事情が、潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当することであるのか否か、が決め手になるということと解されます。
-
本件では、仮に1株当たり10万5068円をX社株式の時価(実勢価格と同義で用います。以下同じ。)というにしても、時価と通達評価額との間に大幅な乖離があり得ること自体は、不動産であれ株式であれ、別件最判の説示するとおり、潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当することです※4。本判決が、上記乖離の有無を公平に判断するためには、他の相続案件も含め、取引相場のない株式その他市場性のない相続財産の全てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的な理由がないのに、特定の相続財産のみについて専門的評価を行い、これを基にして課税処分を行うことは平等原則に反すると説示するのも、このことをいうものと解されます。
-
また、相続の開始(死亡)時期が、売買契約成立の前なのか(この場合は株式の通達評価額で課税)、それとも後なのか(この場合は売却代金≒時価が未収金又は現金として課税)で課税標準が異なるということも、人はいつ亡くなるか分かりませんので、そのこと自体はやはり潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当することです。本判決が、本件は前者の場合であり、相続財産が売買代金債権に転化する蓋然性の程度なるものを問題とするのは適切でないと説示するのも、このことをいうものと解されます。
-
このように、本判決で課税庁が問題視した事情は、いずれも潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当する事情であるといわざるを得ず、別件最判によれば、これらの事情のみをもって平等原則の例外を認めるというのは困難であるといわざるを得ないように思われます。
-
言い換えれば、潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当する事情が仮に問題であるのであれば、それは、上記解説のとおり「評価通達の見直し等によって解消されるべきもの」ということであって、個別事案において総則6項の適用により解決すべき問題ではない※5ということです。このため、冒頭の記事においても、評価通達上の非上場株式の評価ルール自体が見直される可能性につき言及されています。
-
これに対し、別件最判の事案においては、いわば亡くなる間際に多額の借入れやそれによる不動産等の購入といった相続税額の軽減効果を持つ積極的な行為が意図的に行われていました。かかる事情は、潜在的な他の納税者の相続においても広く妥当することであるとはいえず、その結果税負担の著しい不均衡が生じているものとして、平等原則の例外が認められたものということができます。
-
本判決においても、X社株式の評価額を下げるような行為や、売買契約の成立を遅らせる行為がされたことは窺われず、被相続人A及びAの相続人が、相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたと認めることができないことが、総則6項の適用を否定する方向で考慮されています。
-
他方で、本判決には、若干違和感もあります。といいますのも、別件最判を踏まえれば、1株当たり10万5068円は時価といえるかもしれないが、いずれにしても時価と通達評価額との乖離だけでは平等原則違反とはならない、とだけ言えば済む話のはずです。
-
しかし、本判決は、譲渡予定価格である1株10万5068円が交換価値(つまり時価)を反映したものとはいえない云々という、当職の感覚ではそこは問題の本質ではないのではないかと思われる説示をしています(この説示自体、租税法上の時価の定義(大要、非関連の独立の第三者が各々の経済的利害を踏まえて相互に対等に交渉した結果としての価格)からすれば、違和感が拭えないところです。)。
-
また、本判決は、別件最判の射程や解釈に関する一般論(別件最判は租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題にしている、総則6項を納税者の不利に適用するに当たってはその不均衡や不利益等を納税者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が必要と解すべきである等)その他一審判決の説示をほぼ全て削除しています。
-
このことをどう理解するかですが、巷でも諸説あるようですが、当職としては、説示を個別の事実認定の問題にできるだけ絞ることで、本判決は「法令の解釈に関する重要な事項」(民訴法318条1項)を含むものではない(事実認定の問題にすぎない)との体裁をつくり、もって、国側に上告受理申立ての理由を与えないようにしたい、平たくいえば、上に行けないように、万一にも上で破られないようにしたい、という考慮があったのではないか、と見立てています。つまり、一審判決と全く異なる新たな解釈を打ち立てたといったことではないと考えています。実際、国は上告受理申立てをしませんでした。
-
本判決の事案の増額更正処分は、別件最判が出るかなり前になされたものです(平成30年8月7日付け)。別件最判が出る前の議論状況としては、その一審及び原審の判断をはじめとして、通達評価額と時価との乖離の程度という要素を総則6項発動のための主な要素として考慮する考え方がむしろ主流であった※6といえ、今回の増額更正処分もそのような主流であった考え方に依拠したものともいえます。その意味では、今回の課税庁にも同情できるところはあるといえます。もっとも、別件最判が最高裁としての「正しい」解釈を示した以上は、本判決が判示するように、その判断枠組みに従って判断するほかはない(課税庁が大目にみられることはない)と解されます。
-
いずれにしても、本判決を踏まえた今後においては、課税庁における実際の(建前は措いて本音での)判断としては、時価と通達評価額との間に大幅な乖離があることをもっては総則6項は発動できない、というものとなると思われ、その意味では、総則6項の発動にはより慎重が期せられることになるものと思われます。他方で、そのことの裏返しとして、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」としての相続税の負担を減じ又は免れさせる行為が行われたことを裏付ける証拠を、よりアグレッシヴに調査で収集しようとする動きが強まるのではないかと思われます。そのような行為があったか否かは客観的に判断すべき問題ではあるものの、こと調査・更正の段階の実務としては、相続税軽減の意図があったことを示す証拠、例えば取引の検討段階のemailなどにより注目が集まるように思われます。その意味では、近時の法人税法132条の2(組織再編成に係る行為計算否認規定)の発動事案における調査実務(そのようなemailや内部資料が必ずといってよいほど収集されている)と類似してくるようにも思われます。
-
これに対しての納税者側の対応としては、行った取引が客観的には相続税の軽減に繋がったとしても、それは相続税軽減の意図をもって敢えて行ったわけではなく、別の経済的にみて合理的な目的のために行ったといえるのであれば、それは潜在的な他の納税者も広く一般に行い得ることであるという点において、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」を否定する方向に働くのではないかと思われます。この点においても、法人税法132条の2への対応実務と類似してくるように思われます。
-
念のため、本稿においては、総則6項を「適用」するとか、その適用を否定又は肯定するという趣旨の表現を、分かりやすさの観点から便宜用いています。本判決も、総則6項の適用という表現を用いています。しかし、別件最判に照らせば、本件における問題の法的に正しい整理としては、総則6項の適用の可否ではなく(評価通達は法令ではないので)、また時価の認定の如何でもなく(時価は評価通達とは関係なく認定されるものなので)、あくまでも租税法上の一般原則である平等原則の例外が認められるか否かであることには留意が必要です。
脚注一覧
※4
別件最判の考え方によれば、「実勢価格等が通達評価額の何倍であるといった主張立証には意味がない(主張自体失当である)ことになる」とまで解されています(山本拓「判解」法曹時報75巻12号199頁)。
※5
このことを受けて、実際に、いわゆるタワーマンション等の評価について、通達評価額を実勢価格に近似させる通達改正が行われたことは、記憶に新しいところです。
※6
この主流であった考え方を、当職が提出した鑑定意見書において、別件最判が出る前に批判していたことにつき、当職の2022年4月のニュースレター参照。また、当職の2022年12月のニュースレターでは、「通達評価額と実勢価格との大きな乖離はあるが、相続税負担が著しく軽減されるという結果を得る意図は認められないというような事案については、通達評価額によらなくてもよい合理的な理由は認められず、実勢価格による課税は行うことができないということです。要は、事案によっては、[別件最判]と同じようにはいかず、国の敗訴となり得るということです。」と指摘していました(つまり本判決のような判断があり得るということ。)。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
全文ダウンロード(PDF)
Legal Lounge
会員登録のご案内
ホットなトピックスやウェビナーのアーカイブはこちらよりご覧いただけます。
最新情報をリリースしましたらすぐにメールでお届けします。
会員登録はこちら