
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
ニュースレター
<AI Update> 米国におけるAI大統領令発令後の取組みについてのアップデート(2024年3月)
<AI Update> 「欧州AI法」の概要と日本企業の実務対応(2024年6月)
<AI Update> AI発明に対する特許付与について判示した知財高裁判決 ―知財高判令和7年1月30日―(速報)(2025年2月)
<AI Update> 米国著作権局によるAI生成物の著作権保護に関する報告書の公表(2025年2月)
<AI Update> 欧州AI法「禁止されるAIプラクティス」に関するガイドラインの公表(2025年4月)
<AI Update> 米国AI規制の現在地―連邦及び州レベルによる規制の最新動向―(2025年4月)
2025年2月11日、デラウェア地区連邦地方裁判所は、Thomson Reuters v. Ross Intelligence事件※1のサマリージャッジメント(略式判決)(以下「本判決」といいます。)において、2023年9月25日付のサマリージャッジメント※2における判断を修正し、法律検索サービスのヘッドノート(判例要約)をAI学習用データとして利用する行為が著作権侵害に該当し、フェア・ユースの抗弁も認められないとする注目すべき判断を下しました。本判決は、AIの学習段階における著作物利用の適法性について、特に①フェア・ユースの判断における利用目的の判断基準、②AIモデル内における著作物の保持形態と著作権侵害、③AI学習用データの潜在的市場への影響という3つの重要な点で判断を示したものとして、AIの学習段階における著作物利用の実務に影響を与えることが予想されます。
本ニュースレターでは、本判決の判断内容とその意義について紹介いたします。
原告は、米国最大の法律情報データベースの1つであるWestlawを運営しており、被告は、AIを搭載した法律検索サービスを開発するスタートアップ企業です。
Westlawは、判例・制定法・規則・法律雑誌・論文等を収録する法律情報データベースであり、特に判例データベースについては、「ヘッドノート」と「Key Number System」という2つの特徴的な機能を備えています。ヘッドノートとは、各判決の重要な法的論点や判示事項を要約したものであり、原告の編集者が判決文全体から重要な部分を選び出し、簡潔に整理して作成されています。また、原告は各ヘッドノートに「Key Number」という固有の番号を付与し、同じ法的論点を扱うヘッドノートには同じ番号を割り当てることで、体系的な分類システムを構築しています。原告は、これらについて著作権登録を有しています。
一方、被告が開発していたAIを用いた法律検索サービスは、自然言語による検索エンジンであり、ユーザーが法的質問を入力すると、AIが関連する判決文から関連箇所を引用して提示するというものでした。当該サービスは、生成AIのように新しい文章を生成するのではなく、既存の判例から適切なものを選択して表示する仕組みです。
被告は、当初、このAIの学習用データベースを構築するため、Westlawのコンテンツのライセンスを原告に求めました。しかし、原告は、被告が競合となることを理由にこれを拒否しました。そこで被告は、様々な法的論点に関する質問と回答をまとめ、関連する判例を特定した文書である「Bulk Memos」を作成するよう、第三者の法律調査会社に委託しました。当該法律調査会社は、作成にあたってWestlawのヘッドノートを使用して質問を作成することを作業者に説明する一方で、ヘッドノートを直接コピー&ペーストしないよう指示していました。被告は、このようにして作成された約25,000点のBulk MemosをAIの学習に使用しました。原告は、この事実を知った後、被告に対して著作権侵害訴訟を提起しました。
裁判所は、2023年9月25日付のサマリージャッジメント(以下「2023年サマリージャッジメント」といいます。)において、ヘッドノートの創作性に関する判断に必要な判決文からの選択・整理の程度や、AIによる学習利用が変容的利用(transformative use)に該当するか等の重要な争点について、陪審による事実認定を要するとして、著作権侵害及びフェア・ユースの成否に関するサマリージャッジメントの申立てを概ね否定しました。その後、裁判所は事案をより詳細に検討した結果、一部の争点については陪審による事実認定を要せず裁判所が法的判断を行うことが可能であると判断を改め、当事者に改めてサマリージャッジメントの申立てを行うよう求めました。この申立てに基づき、裁判所は2025年2月11日、一部の争点について本判決を下すに至りました。
裁判所は、原告の申立てを一部認容し、①ヘッドノートについて最小限度の創作性が認められること、②検討対象とした2,830件のヘッドノートのうち少なくとも2,243件について著作権侵害が認められること、③フェア・ユースの抗弁が認められないことを判示しました。
裁判所は、ヘッドノートの著作物性を認めました。裁判所は、ヘッドノートが個別の著作物としても編集著作物としても、著作権保護に必要な最小限度の創作性の基準を満たすと判断しました。判決文自体は著作権の対象とならないものの、判決文から重要な法的論点を選択し、要約・分析する編集者の判断には創作性が認められるとしました。さらに、判決文から逐語的に引用された部分であっても、長文の判決全体から特定の部分を選び出すという判断それ自体が、その判決における重要な法的論点に関する編集者の考えを表現するものとして、著作権保護に値する創作性が認められるとしています。
また、Key Number Systemについても、法的分野の分類方法として可能な選択肢の中から特定の方法を選択したことに最小限度の創作性が認められるとしました。
裁判所は、著作権侵害が主張された約21,787件のヘッドノートのうち、原告がサマリージャッジメントを申し立てた2,830件について、Bulk Memo、ヘッドノート、元の判決文を詳細に比較検討しました。その結果、2,243件について、Bulk Memoの質問がヘッドノートの文言に極めて近似する一方で判決文の文言とは異なっているため、実質的類似性の判断について合理的な陪審であれば他の結論に達し得ないほど明白であるとして、著作権侵害を認めました※3。
具体的には、①実際の複製(actual copying)と②実質的類似性(substantial similarity)の2点について検討を行いました。実際の複製については、委託先である法律調査会社がWestlawにアクセスしてBulk Memosを作成していた事実に加え、Bulk Memoの質問が元の判決文よりもヘッドノートにより類似していることが、複製の存在を示す強力な状況証拠になるとしました。実質的類似性については、裁判官自身が法律家としてWestlawのヘッドノートの通常の利用者であることから判断が可能であるとした上で、2,830件のヘッドノートのうち2,243件について、ヘッドノートの言語表現がBulk Memoに極めて近似しており、かつ判決文の文言とは異なっていることから、実質的類似性が認められると判断しました。
なお、Key Number Systemの利用や他のヘッドノートに関する侵害の有無等については、事実関係に争いがあるとして、判断を留保しました。
被告は、抗弁として、フェア・ユースに該当するため著作権侵害には該当しないと主張しましたが、裁判所は、フェア・ユースの判断において考慮すべき4つの要素※4を検討し、第1要素と第4要素が特に重要であるとした上で※5、フェア・ユースの抗弁を否定しました。
裁判所は、本要素は原告に有利であると判断しました。被告による利用が商業的な性質を有することは争いがなく、また、変容的利用(transformative use)も認められないとしました。裁判所は、「被告は、競合する法律検索ツールの開発を容易にするためにヘッドノートを利用した」と指摘し、被告による利用は、原告がヘッドノートを作成した目的である法律検索の促進と本質的に同じ目的であると判断しました。
被告は、ヘッドノートはAI学習の過程で数値データに変換されて中間的に利用されたに過ぎず、最終的なサービスにはヘッドノートが表示されないと主張しました。しかし裁判所は、このような中間的な利用であっても、その最終的な目的が「判例を検索すること」にあり、これは原告のヘッドノートとKey Number Systemが意図した目的と同じであるとしました。また、コンピュータプログラムの互換性確保のための中間的複製が認められたSony判決やSega判決などの先例※6と本件を区別し、①先例はプログラムの機能的要素へのアクセスが必要な事案であり、本件のような文章の利用とは異なること、②先例では複製が技術的に必要不可欠であったのに対し、本件では被告が独自の要約や分類体系を開発することも可能であり、単に原告の既存の成果を利用する方が便利だったに過ぎないことを指摘しました。
裁判所は、本要素は被告に有利であると判断しました。ヘッドノートは編集に創作性が認められるものの、小説家や芸術家が一から創作する著作物と比べると、創作性の程度は相対的に低いとされました。
裁判所は、被告のサービスにおいて、ヘッドノートが最終的な出力に含まれる形で公衆に提供されることはないことから、本要素は被告に有利であると判断しました。裁判所は、重要なのは複製の過程で利用された量や実質性ではなく、公衆にアクセス可能となり競合する代替物となりうる部分の量や実質性であるとしています。
裁判所は、本要素は原告に有利であると判断しました。裁判所は、問題となる利用行為が著作物の現在の市場に与える影響だけでなく、派生的な市場への影響も考慮すべきとした上で※7、被告は競合するサービスを開発する目的でヘッドノートを利用しており、また、AI学習用データのライセンス市場という潜在的な市場への影響も認められるとしました。被告は法情報へのアクセスという公益性を主張しましたが、裁判所は、判例等の法律の内容それ自体は自由にアクセス可能であり、原告が作成した法的分析(ヘッドノート)を無償で利用する権利は認められないとして、この主張を退けました。
裁判所は、第1要素と第4要素が原告に有利であり、これらの要素が特に重要であることを重視しました。そして、第2要素と第3要素が被告に有利であることを考慮してもなお、総合的な衡量においてフェア・ユースは認められないと結論付けました。
裁判所は、被告のその他の主張についても、それぞれ以下の理由から否定しました。
Westlawのヘッドノートには著作権表示が付されていたため、善意の侵害は適用されない。
原告が競争を制限する目的で著作権を行使したとの証拠はない。
判決文における法的論点は様々な方法で表現できる。
判決文の要約方法は1つに限定されず、原告の方法に従う必然性はない。
本判決は、AIの学習用データとして著作物を利用する行為について、①中間的利用という形態ではなく、プロジェクト全体としての目的に着目してフェア・ユースの判断における利用目的を評価し、②AIモデル内での著作物の保持形態が著作権侵害を否定する根拠とはならないとし、③AI学習用データの潜在的市場への影響を重視するという、3つの重要な判断基準を示しました。これらの判断は、今後のAI開発における著作物利用の実務に大きな影響を与える可能性があります。
フェア・ユースの判断における利用目的の評価において、裁判所は、AI学習の過程における中間的な利用形態ではなく、プロジェクト全体としての目的を評価しました。すなわち、ヘッドノートが最終的な出力として表示されないことや数値データに変換されることではなく、競合する法律検索サービスの開発という目的に着目し、変容的利用を否定しました。
この判断は、2023年サマリージャッジメントとは異なる考え方を示すものです。2023年サマリージャッジメントでは、Sony判決やSega判決における中間的複製の判例法理に基づき、①言語パターンの分析学習のための利用であれば変容的利用となる可能性がある一方、②Westlawの編集者の創造的な判断の複製が目的であれば変容的利用とはいえないとした上で、被告がWestlawとは異なる目的を持つ全く新しい研究プラットフォームを作り出した可能性があることから、その性質の判断には事実審理が必要とされました。
これに対し本判決では、Sony判決やSega判決の事案は、①コンピュータプログラムの複製に関する事案であり、②基礎となるアイデアにアクセスするために複製が必要な事案であったが、本件ではそれらに該当しないとして、これらの先例が適用されないと判断しました。その上で、Warhol判決※12の枠組みに基づき、原著作物(ヘッドノート)と二次的利用が同じような目的(法律検索)を持ち、その利用が商業的性質を持つことや、複製行為が利用者の新たな目的を達成するために合理的に必要であるとは言えないことから、変容的利用を否定しました。
本判決は、上記のフェア・ユース判断において、被告がヘッドノートを数値データに変換したという事実は、著作権侵害を否定する根拠とはならないと判示しました。この考え方は、著作物がAIモデル内でアルゴリズム的・数学的な表現に変換されていたとしても、それは単に著作物が異なる手段(medium)で固定されているに過ぎないという2024年のAndersen v. Stability AI事件での判断と同様であり※13、AI開発における著作物利用の法的評価に関する重要な判断基準を示すものといえます。
フェア・ユースの判断において、裁判所は、第4要素である著作物の潜在的市場への影響の考慮にあたり、現時点で確立していないAI学習用データのライセンス市場への影響をも考慮しました。2023年サマリージャッジメントでは、被告の利用が市場代替とならない可能性や、原告が自身のデータをAI学習に利用する可能性について事実審理が必要とされていましたが、本判決では、被告はWestlawの市場代替物を開発する意図を持っており、また、原告が当該データを法律検索ツールのAI学習に利用しているか否かに関わらず、AI学習用データの潜在的な市場への影響があれば十分であると判断を変更しました。これは、著作権者がAI学習用データのライセンスビジネスを展開する可能性を保護する必要性を認めたものです。
現在、米国では30件以上のAI関連著作権侵害訴訟が連邦裁判所に係属しているといわれています。その多くは、生成AI開発企業による著作物の無許諾利用が著作権侵害に該当するかが争点となっており、Getty Images v. Stability AI、New York Times v. OpenAI、Concord Music Group v. Anthropic等、画像、テキスト、音楽等様々な分野の著作物について訴訟が提起されています※14。フェア・ユースの判断は個別の事実関係に基づいて行われるものであり、また、本判決は生成AIではなく伝統的な法律検索AIに関する事案であったことから、今後、生成AI等の異なる類型のAIについて、AIモデルの機能や著作物の種類に応じてフェア・ユースの判断がどのようになされるか、引き続き注目されます。
※1
Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., No. 1:20-cv-613-SB (D. Del. Feb. 11, 2025)
※2
Thomson Reuters Enter. Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., 694 F. Supp. 3d 467 (D. Del. 2023)
※3
裁判所は、実質的類似性の判断は通常、事実認定の問題として陪審に委ねられるべきものであるとしつつ、“summary judgment can be ‘appropriate’ when ‘no reasonable jury could find’ otherwise”として、本件ではその例外的な場合に当たると判断しています(本判決書13頁)。
※4
17 U.S.C. § 107(米国著作権法第107条)は、フェア・ユースの判断において考慮すべき要素として、(1)使用の目的及び性質、(2)著作物の性質、(3)使用された部分の量及び実質性、(4)著作物の潜在的市場価値への影響を規定しています。
※5
Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202, 220 (2d Cir. 2015) を引用
※6
Google LLC v. Oracle Am., Inc., 593 U.S. 1 (2021) (APIの互換性確保のためのコードの複製)
Sony Computer Ent., Inc. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000) (ソニーのゲーム機ではなくパソコンでゲームをプレーできるようにするためのソースコードの複製が変容的利用として認められた事例)
Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992) (既存のゲームシステムと互換性のあるゲームを作成するためのソースコードの複製が変容的利用として認められた事例)
これらはいずれも、ソフトウェアの互換性確保のために技術的に必要な中間的複製が問題となった事案です。
※7
“I must consider not only current markets but also potential derivative ones ‘that creators of original works would in general develop or license others to develop.’” 本判決書21頁(Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 592 (1994) を引用)
※8
著作権侵害が善意でなされた場合に損害賠償額を制限する抗弁
※9
著作権者が公共の利益に反して著作権を濫用的に行使している場合に認められる抗弁
※10
アイデアを表現する方法が限られている場合、そのアイデアと表現が一体(merge)となり著作権保護が否定されるという抗弁
※11
特定のジャンルや場面で必然的に使用される表現については著作権保護が否定されるという抗弁
※12
Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023)
写真家の作品を基に作成されたアート作品のフェア・ユースを否定した最高裁判決で、二次的著作物が原著作物と「同一又は非常に類似した目的」を持ち、その二次的利用が商業的性質を持つ場合、他に複製を正当化する理由がない限り、第1の要素(利用の目的及び性質)はフェア・ユースに不利に働く可能性が高いとする基準を示しました。また、複製行為が利用者の新たな目的を達成するために合理的に必要であるかという観点も、判断において重要であるとしています。
※13
“That these works may be contained in Stable Diffusion as algorithmic or mathematical representations – and are therefore fixed in a different medium than they may have originally been produced in – is not an impediment to the claim at this juncture.” Andersen v. Stability AI Ltd., No. 23-CV-00201-WHO, 2024 WL 3823234 (N.D. Cal. Aug. 12, 2024) 17頁
※14
Getty Images v. Stability AI, Ltd., (No. 23-CV-00135)、The New York Times Company v. OpenAI, Inc., (No. 23-CV-11195)、Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC, (No. 23-CV-01092)等
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
髙取芳宏


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


(2025年10月)
東崎賢治
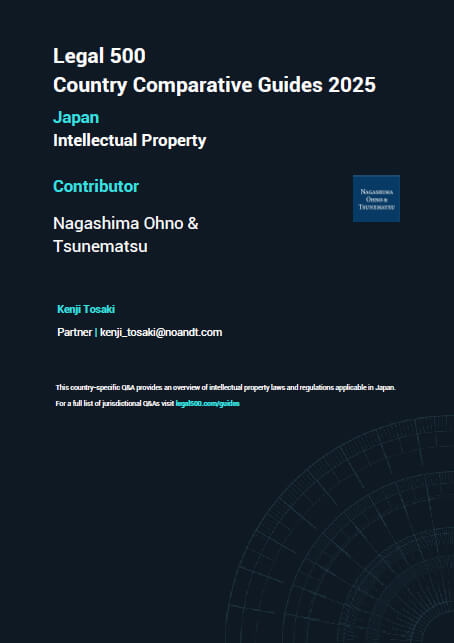
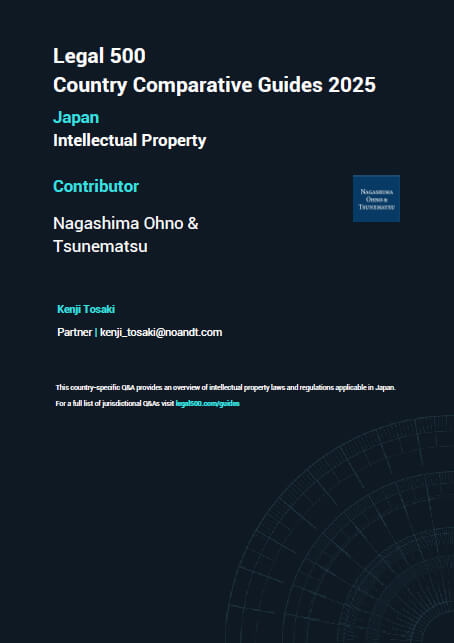
(2025年9月)
東崎賢治


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


梶原啓


クレア・チョン、加藤希実(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


井上聡、松永隼多(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)