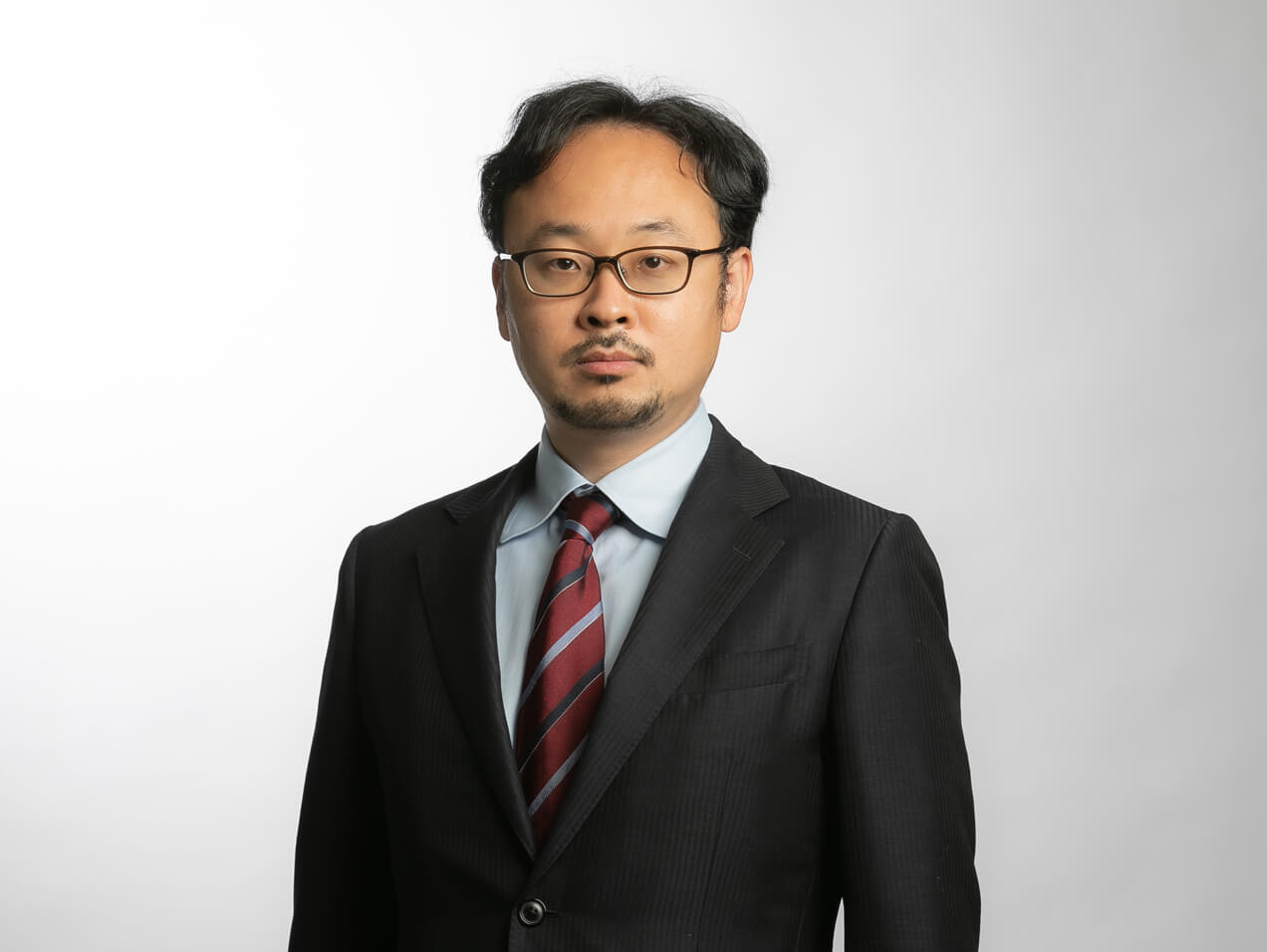
細川智史 Satoshi Hosokawa
パートナー
東京

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
ニュースレター
セキュリティ・クリアランス法案の概要(小林鷹之議員及び立法担当官と語る経済安全保障の最前線セミナーに向けて)(2024年5月)
セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理(前編) ~従業員の新規募集・採用時の留意点~(2025年2月)
特集
経済安全保障
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(以下「法」又は「重要経済安保情報保護活用法」といいます。)において機密情報の指定対象となる「重要経済安保情報」の取扱いの業務は、内閣総理大臣による調査を踏まえて行政機関の長が実施する適性評価(法12条1項)において、当該情報を「取扱った場合に漏らすおそれがないと認められた者」に限って行うことができます(法11条1項)。
本ニュースレターの前編※1では、適合事業者が重要経済安保情報を取り扱う業務に就かせることを想定して新たに従業員を募集・採用しようとする場合の留意点について論じました。本ニュースレターでは既存の従業員を当該業務に割り当て、又は当該業務を委託しようとする場合の留意点について解説いたします。
行政機関の長が適性評価を実施するためには、評価対象者の任意かつ真摯な同意を取得することが必要とされています(法12条3項)。そのため、会社が従業員にクリアランス取得のための適性評価を受けるよう依頼しても、当該従業員が重要経済安保情報の取扱いの業務への従事を拒否する目的又はそれ以外の目的で適性評価の実施に同意しない場合、その結果として当該従業員を当該業務に従事させることができないという事態が生じ得ます。また、従業員が適性評価の実施に同意した場合でも、適性評価の結果、クリアランスを取得できなければ、やはり重要経済安保情報の取扱いの業務に従事させることはできなくなります。
そこで、会社が重要経済安保情報を取扱う業務に他の部署から従業員を割り当てる場合には、当該従業員の適性評価の結果を待ってから当該業務への配転を命ずることが基本的な方向性になると考えられます。他方で、従業員が現在所属している部署で新たに重要経済安保情報を取扱う業務が発生するケースも考えられます。そうしたケースにおいて、当該従業員が適性評価の実施に同意せず、又は適性評価の結果が不合格となった場合、当該従業員に配転を命ずることは可能でしょうか。
一般論として、使用者は、就業規則や従業員との労働契約に使用者が配転命令権を有する旨の規定を定めた場合、従業員との間で職種や勤務地を限定する旨の合意(職種限定合意)をしているといった特別な事情がない限り※2、原則として、当該従業員の個別の同意がなくとも配転を命じることができます。ただし、配転に業務上の必要性がない場合、不当な動機・目的が認められる場合、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等は、労働法上の権利濫用法理により配転命令権の行使が制限されます。さらに、重要経済安保情報保護活用法との関係でも、使用者は適性評価の結果を「重要経済安保情報の保護以外の目的のために」利用・提供することはできないとされており(法16条2項)、かかる目的外利用の一環として「不利益な配置の変更」が含まれると解されているため(2025年1月31日付「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準※3」(以下「運用基準」といいます。)4章4節3)、その点においても配転が無限定に実施できるわけではありません。
したがって、従業員が現に所属する部署においてクリアランスが必要であるにもかかわらず、当該従業員が適性評価の同意を拒否し、又は適性評価が不合格となった場合、原則として配転を行う業務上の必要性は認められると思われますが、配転先について合理性があり、従業員に「不利益」にならないよう留意が必要です。
この点に関して、2025年1月31日に公示された、運用基準案のパブリック・コメントに対する回答※4(以下「運用基準案のパブリック・コメント」といいます。)では、「重要経済安保情報を取り扱う部署であっても、実際に重要経済安保情報を取り扱う必要のない業務がある場合も想定され、こうした場合において、適性が認められなかった者を部署異動させることは、目的外利用に当たる可能性もある」とされていますが 、重要経済安保情報を取り扱う部署においてクリアランスを持たない従業員が業務を行うことは、部署内の情報管理等に相応のコストを要する可能性もあることから、個別の事情によっては、かかる配転が許容されるべき余地は相応にあると考えられます。また、配転先次第では(例えば、減給もない上に当該従業員の能力や経歴などに照らして合理的な配転先である場合)、そもそも「不利益」ではないともいえる場合もあるのではないかと思われます。
加えて、前述した「不利益な配置の変更」を含め、適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限として、下記のとおり、適正評価の結果を考慮した解雇、自宅待機命令、労働契約内容の変更の強要など、幅広い行為が禁止されているため、留意が必要です。
適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限(運用基準4章4節3)
適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、次に掲げる場合を除き、評価対象者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(略)
適性評価の実施に当たって取得する個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供するとは、例えば、適性評価の結果を考慮して、解雇、減給、降格、懲戒処分、自宅待機命令、不利益な配置の変更、労働契約内容の変更の強要、昇進若しくは昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと、又は専ら雑務に従事させるなど就業環境を害することなどが考えられる。
本ニュースレターの前編では、適合事業者が重要経済安保情報を取り扱う業務に就かせることを想定して新たに従業員を採用しようとする場面において、適性評価の結果を予測する目的で採用対象者の個人情報を収集することができるか否かについて議論しました。それでは、新たに従業員を採用するのではなく、既存の従業員を当該業務に割り当てようとする場合、同様の目的で情報を収集することは許容されるでしょうか。
本ニュースレターの前編で解説したとおり、適性評価調査の対象となる事項(法12条2項各号)に係る情報には、精神疾患(病歴)、犯罪の経歴など「要配慮個人情報」(個人情報保護法2条3項、個人情報保護法施行令2条)が含まれるため、既存の従業員についても、これらの情報を取得するためには、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があることに変わりはありません(個人情報保護法20条2項)。もっとも、既存の従業員に関する情報収集については、新規の採用対象者に関して適用のある職業安定法の規律は及ばないことになります(本ニュースレターの前編参照)。そこで、従業員から個人情報保護法に基づく同意を得た上、当該情報を、クリアランスが必要な業務に従事させるか否かという判断のために必要な範囲で収集し、それを利用する場合には、業務上必要な合理的な範囲の収集・利用であるとして許容されるべきではないかと考えられます。
なお、適性評価調査において評価対象者が記入する質問票の記載事項には、本人及び家族の「日本国籍」、「帰化歴」及び「外国籍」等が含まれており(運用基準別添5)、評価対象者の国籍が適性評価の考慮要素になると思われます。運用基準案のパブリック・コメントでは、「評価対象者の国籍が外国籍であることのみをもって、直ちに適性があると認められないと判断されるわけでな」いとされていますが(131番ないし133番)※6、実態としては、外国籍の者にクリアランスが付与される場面は限定的ではないかと思われます。そのため、制度施行後の運用動向も注視する必要がありますが、クリアランスが付与される可能性や適性評価調査に係る対応コスト等を踏まえた判断として、外国籍の従業員を重要経済安保情報の取扱いの業務に従事させる候補者に含めないと判断することも不合理とまではいえず、国籍を理由として、合理的な理由なく、労働者を他の者に比して有利又は不利益に取り扱うことを禁ずる労働基準法3条にも抵触しないと整理することも合理的といえる場合もあるのではないかと思われます。
重要経済安保情報を取扱う業務の性質によっては、当該業務の全部又は一部を外部事業者に委託することも考えられます※7。この場合、重要経済安保情報保護活用法における適性評価の対象について、どのように考えればよいでしょうか。
この点、適合事業者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせることができる「従業者」(法10条3項)は、必ずしも適合事業者と雇用関係にある必要はなく(文言上も「従業員」とはされていません。)、例えば、取締役や執行役員は、適合事業者自身の「従業者」に含まれ、適性評価に合格すれば重要経済安保情報を取扱う業務に従事することが可能と考えられます。また、当該適合事業者の下で働く派遣労働者も「従業者」に含まれると考えられます。他方で、適合事業者から委任を受けて当該事業者の特定の業務に従事する弁護士、コンサルタント、公認会計士、弁理士、大学教員等の外部有識者は、適合事業者の「従業者」ではなく、「それぞれの所属先として別途適合事業者として認定される必要があり、当該別途の適合事業者の従業者として適性評価を得」る必要があるとされています(運用基準案のパブリック・コメント83番)。
また、業務受託者が適合事業者であっても、適合事業者相互間で重要経済安保情報を提供し合うことはできないこととされており、いずれの適合事業者も、あくまで行政機関を起点として重要経済安保情報の提供を受ける必要がある点に留意が必要です※8。この点に関連して、特定秘密保護法の運用では、防衛装備庁から請け負った業務について、防衛装備庁・元請事業者・下請事業者の三者間で秘密保護契約を結ぶことが認められています(「防衛産業保全マニュアル」※9 13章)。重要経済安保情報保護活用法の下でも、かかる運用と同様に、適合事業者から他の適合事業者に対して重要経済安保情報を取扱う業務を委託する場合には、行政機関、元請事業者たる適合事業者、及び下請事業者たる適合事業者の三者間において、以下の事項を含む重要経済安保情報を提供するための契約を締結するといった運用が採られる可能性があります。重要経済安保情報を取扱う業務に関して外部事業者を利用する際には、このような運用の存在も踏まえて行政機関との契約内容等を検討する必要が出てくるでしょう。
重要経済安保情報を提供するための契約に含めなければならない事項(運用基準5章1節4)
今般のセキュリティ・クリアランス制度に関して、民間事業者は、クリアランスが必要な業務に従事させる又はその予定の従業者について、労働法や個人のプライバシーまで考慮に入れた人事労務管理を行うことが求められています。本ニュースレターでは、人事労務管理に関連して想定される論点についてこれまでの当局見解や労働法上の考えなどを踏まえて私達の考えをお伝えしましたが、これらの論点に関しては、今後当局からガイドラインやQ&A等が公表される可能性もあるため、それらの動向にも注視する必要があります。
なお、民間事業者においては、事業者に対するクリアランスであるところの「適合事業者」(法第10条第1項)の認定のために、経営レベルにおいても適切な社内体制を構築していく必要があります。この点については、次回以降の弊所のニュースレターにおいて取り扱う予定です。
※1
国際通商・経済安全保障ニュースレターNo.25(2025年2月)「セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理(前編) ~従業員の新規募集・採用時の留意点~」(細川智史・大澤大・湯浅諭・岡田忠志)
※2
労働法ニュースレターNo.17 / 紛争解決ニュースレターNo.24(2024年7月)「職種限定合意が認められる場合の配転命令の可否–令和6年4月26日最高裁判決(滋賀県社会福祉協議会事件最高裁判決)の概要–」(清水美彩惠・田口涼太)
※5
運用基準案のパブリック・コメント161番
※6
高市経済安全保障担当大臣(当時)も、国会答弁(参・内閣委 令和6年4月3日)で「適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断されることとなります。」と説明しています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121304889X00720240403/5
※7
なお、重要経済安保情報の取扱いの業務の委託自体が禁止されていないことは、運用基準案のパブリック・コメントで明示的に確認されています(210番)。
※8
「適合事業者から他の適合事業者に重要経済安保情報を提供することはできません。この場合、行政機関から直接当該他の適合事業者に当該重要経済安保情報を提供することになります。」とされています(運用基準案のパブリック・コメント254番)。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


(2025年9月)
若江悠


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)