
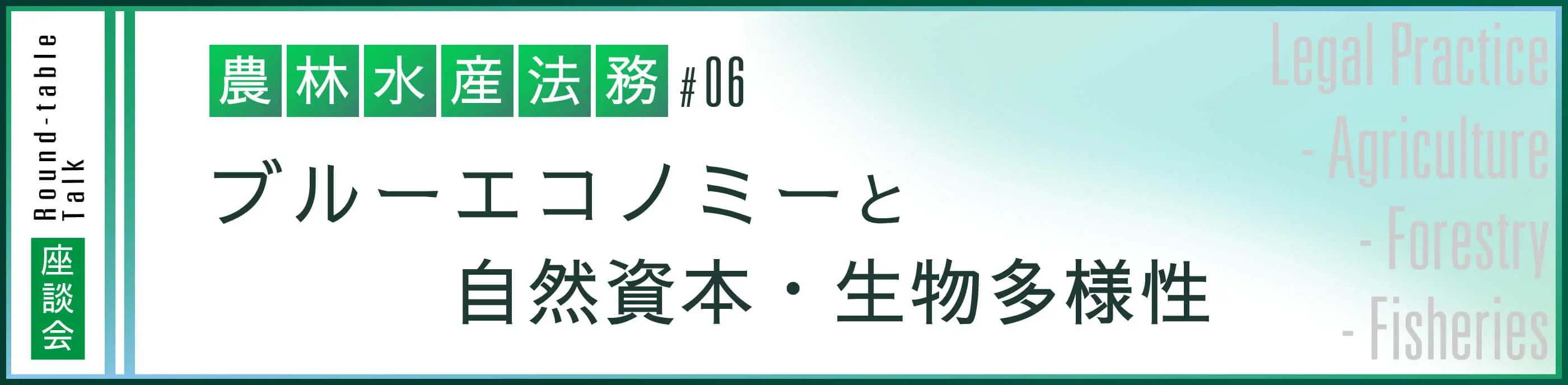
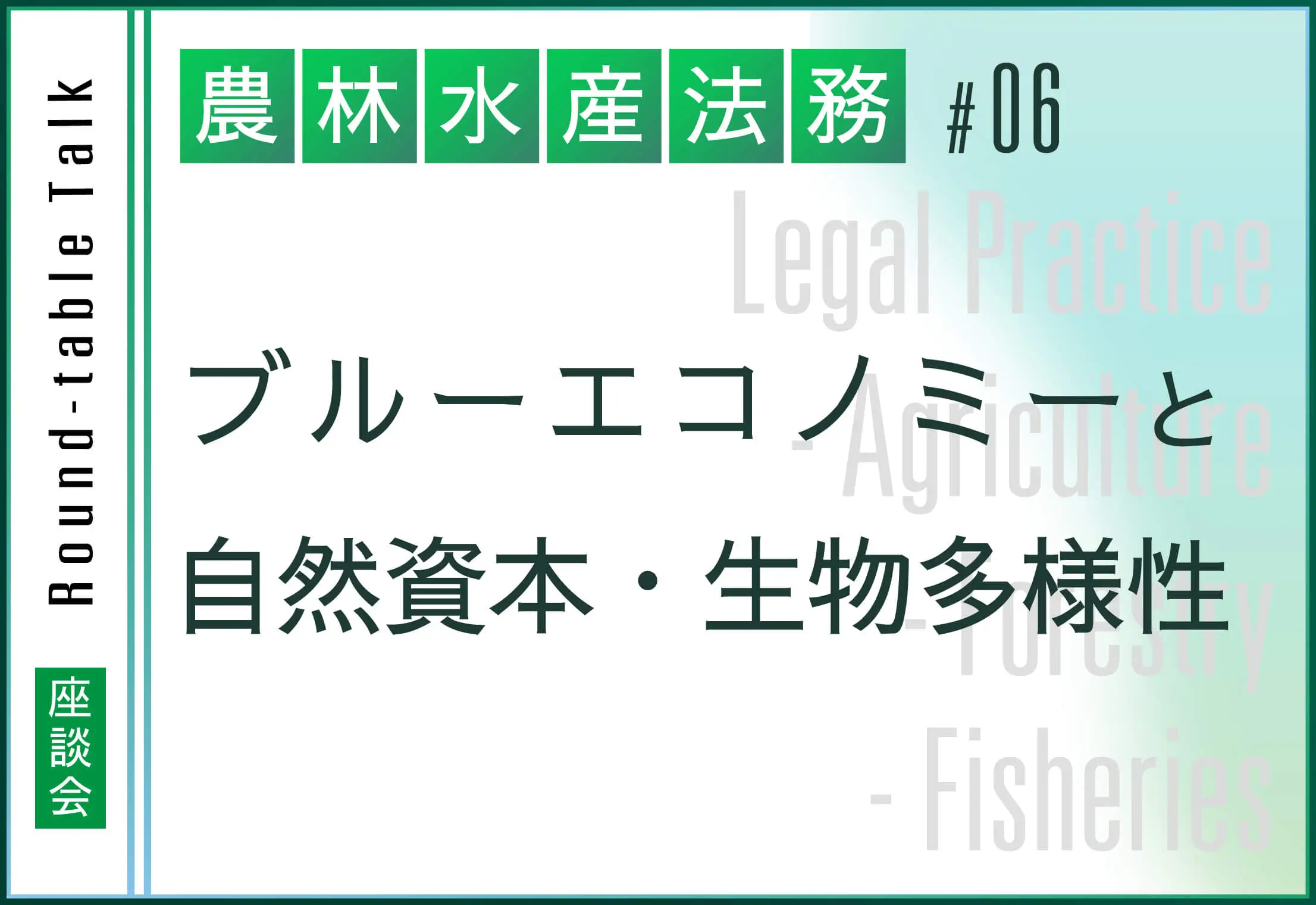
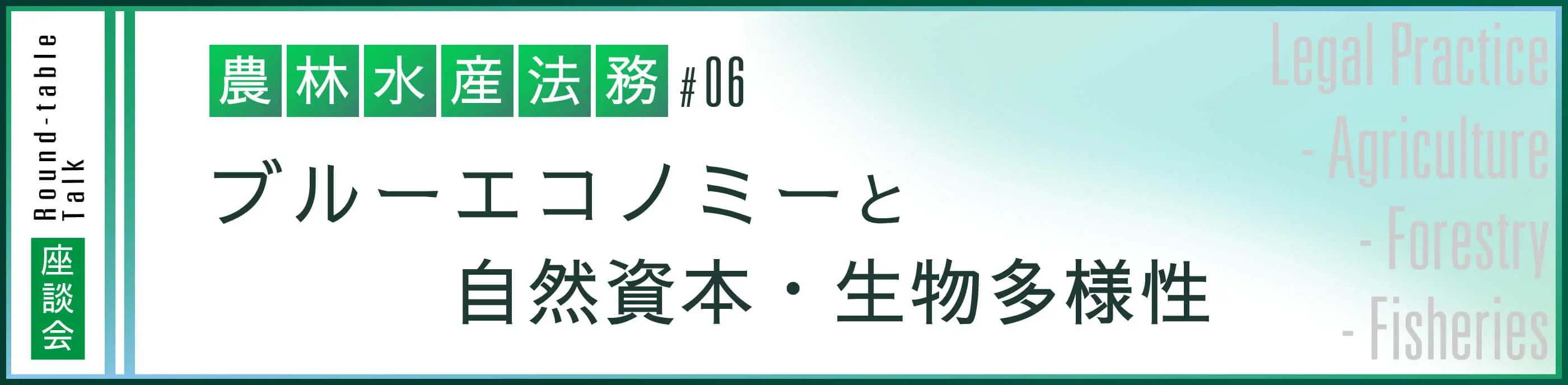
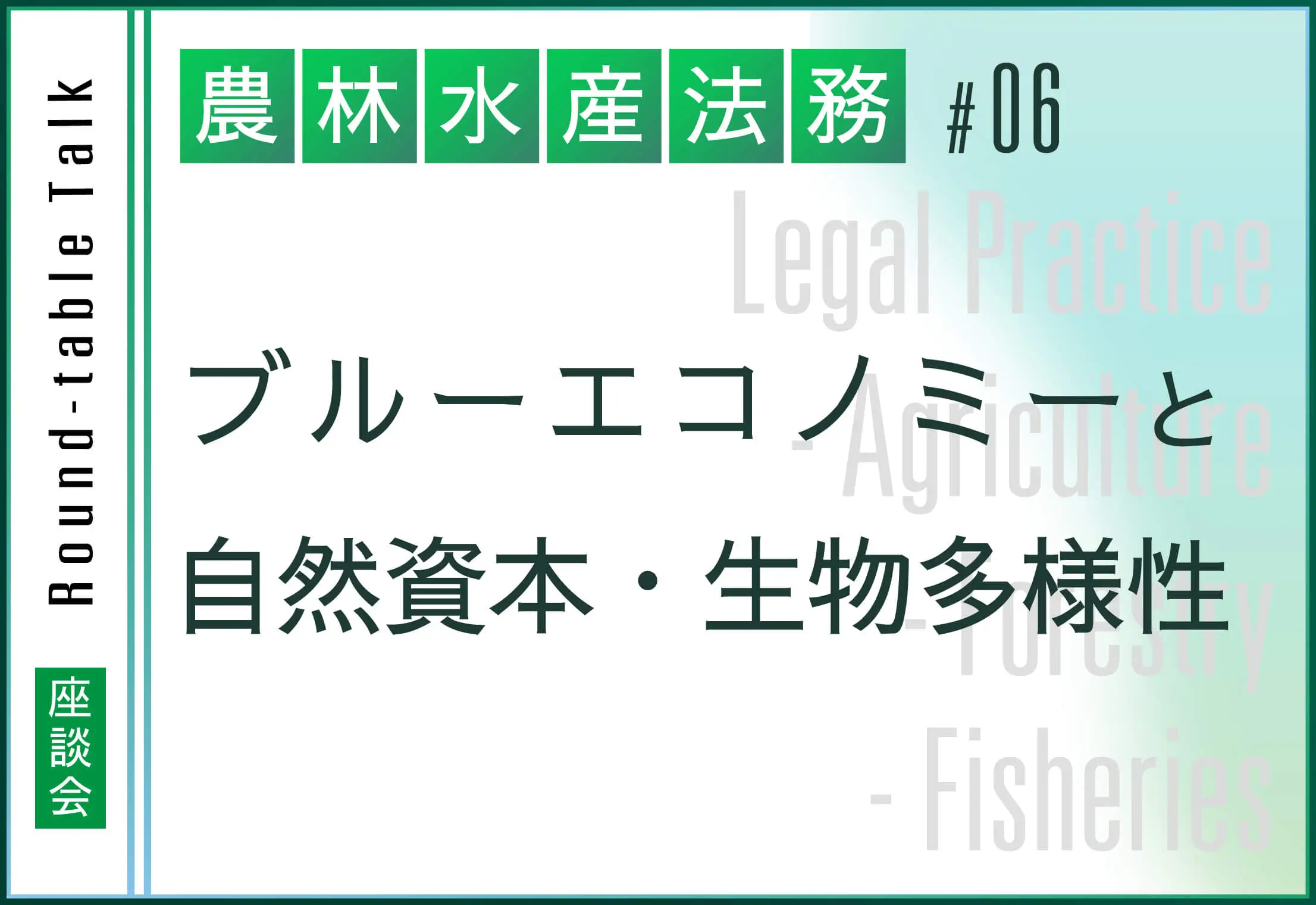

気候変動問題、生物多様性保全、人的資本経営といったサステナビリティの重要テーマの企業情報開示について、国内外の資本市場におけるエクイティ・デット双方のキャピタルマーケット案件、金融規制法、コーポレートガバナンス等の分野の経験を踏まえた実践的な助言に取り組む。

資源・環境・エネルギー、建設・インフラ、プロジェクトファイナンス、証券化・ストラクチャードファイナンス、不動産取引を中心として一般企業法務全般を取り扱うほか、気候変動問題、海洋資源保護や生物多様性保全に関連する法務問題に取り組む。

国内外の資本市場におけるエクイティ・デット双方のキャピタルマーケット案件・企業情報開示及び関連する金融規制法、不動産取引、上場リート・私募リートを中心として、企業法務全般を取り扱う。

M&A/企業再編、不動産取引、上場リート、一般企業法務を中心に、国内及び国外の企業法務全般についてリーガルサービスを提供している。

インフラプロジェクト、環境、一般企業法務を中心に、国内及び国外の企業法務全般についてリーガルサービスを提供している。
農林水産法務シリーズでは、これまで以下の様々なテーマを議論していきましたが、最終回となる第6回は、ブルーエコノミーと自然資本・生物多様性の2つのテーマについて議論していきたいと思います。

田澤

渡邉

星野

渡邉

室

宮下

室

田澤

室

星野

渡邉

田澤

渡邉

田澤

室

渡邉

室

渡邉

宮下



宮下

星野

渡邉

星野

宮下

田澤

星野

宮下

星野

室

星野



渡邉

宮下

田澤

宮下

室

星野

宮下
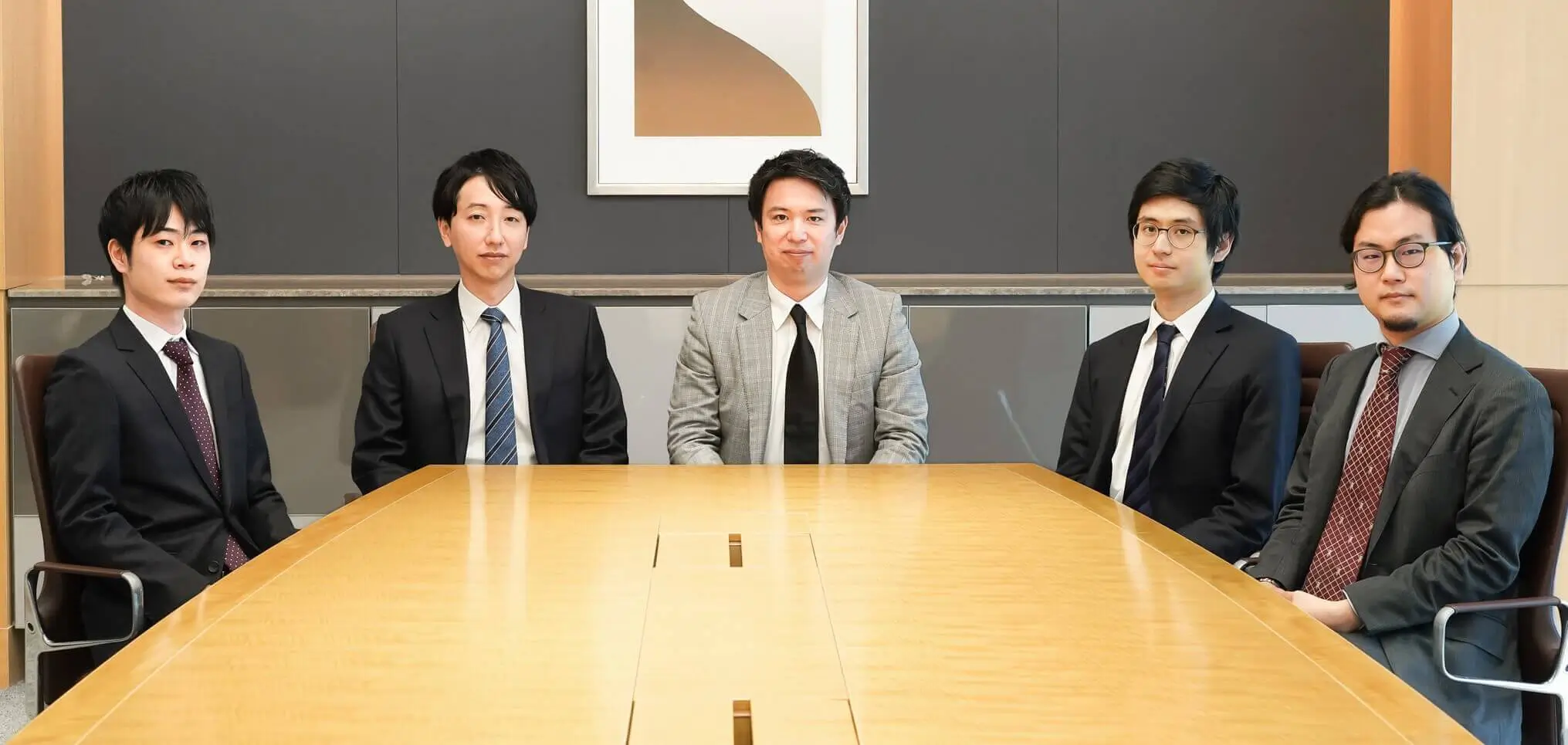
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。