
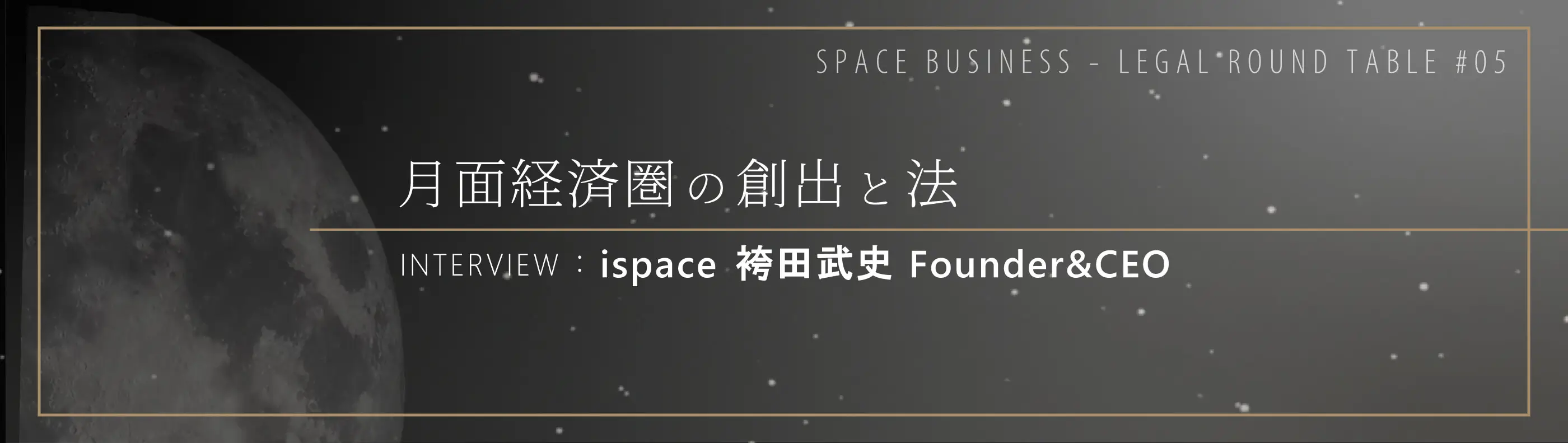

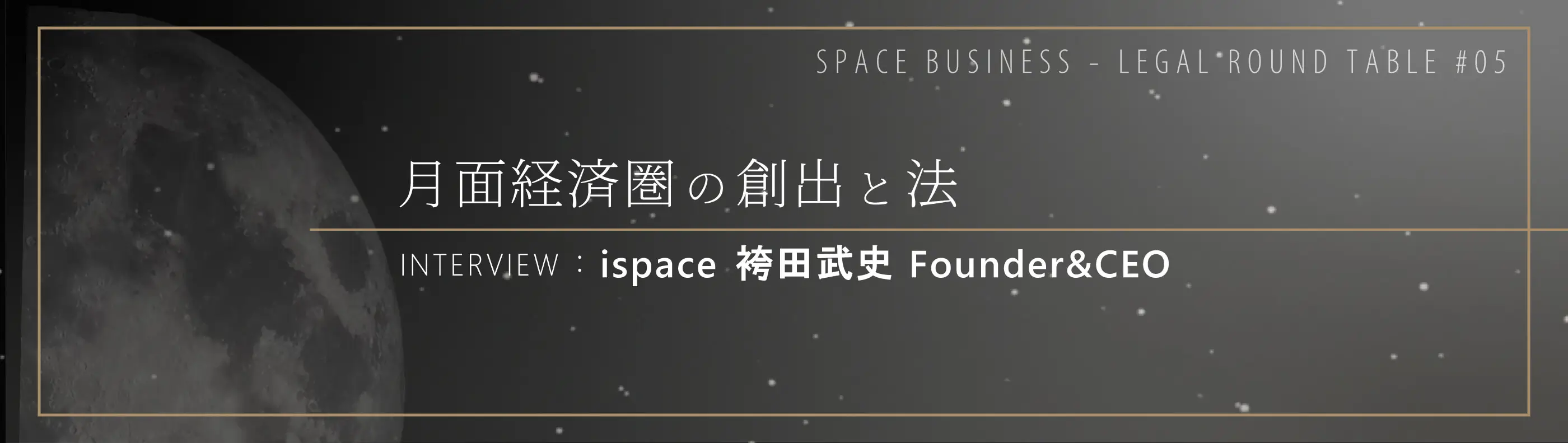


子供の頃に観たスターウォーズに魅了され、宇宙開発を志す。ジョージア工科大学で修士号(航空宇宙工学)を取得。大学院時代は次世代航空宇宙システムの概念設計に携わる。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て2010年より史上初の民間月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」を率いた。同時に、運営母体の組織を株式会社ispaceに変更する。現在は史上初の民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を主導しながら月面輸送を主とした民間宇宙ビジネスを推進中。宇宙資源を利用可能にすることで、人類が宇宙に生活圏を築き、地球と月の間に持続可能なエコシステムの構築を目指し挑戦を続けている。

当事務所宇宙プラクティスグループ代表。主な業務分野は、M&A、プライベート・エクイティ投資、プライベート・エクイティ投資、テクノロジー・宇宙分野などの複雑な企業法務全般である。2010年から宇宙航空研究開発機構(JAXA)契約監視委員会委員。

2018年慶應義塾大学法科大学院卒業。2019年長島・大野・常松法律事務所入所。入所後、キャピタルマーケット、M&A、危機管理・コンプライアンス分野等、様々な分野の案件に従事。当事務所宇宙プラクティスグループの一員として、複数の宇宙分野の案件にも関わっている。

大久保

袴田氏

松本

袴田氏

松本

袴田氏

松本

袴田氏

松本

袴田氏

大久保

袴田氏

松本

袴田氏

大久保

袴田氏

松本

袴田氏

松本



大久保

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保

大久保

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保


松本

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保

袴田氏

大久保

本鼎談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。