
山中淳二 Junji Yamanaka
パートナー
東京

NO&T Real Estate Legal Update 不動産ニュースレター
NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター
NO&T Real Estate Legal Update ~不動産ニュースレター~ 創刊のご案内
長島・大野・常松法律事務所は、今般「NO&T Real Estate Legal Update ~不動産ニュースレター~」を創刊いたしました。本ニュースレターでは、今後、不動産取引、不動産ファイナンス、ホテル、物流施設その他各種不動産の開発・運営、不動産投資/証券化、J-REIT等不動産に関する様々な法律実務上のトピックをお伝えしていきます。
不動産法務は、伝統的な法分野でありますが、その一方で、急速な変容が続く社会動向に対応するための関連法令等の改正や実務の見直しも頻繁に行われており、新たな仕組みや実務上の工夫も含めて注視すべき事項は多岐にわたります。また、日本国内だけでなくグローバルマーケットにおける不動産市場動向も踏まえた対応も求められるようになっています。
当事務所では、これまでも不動産に関連する法制度や実務の動向を各種媒体で紹介してきましたが、不動産法務におけるダイナミズムを踏まえ、不動産法務にフォーカスしたニュースレターの創刊の必要性を感じるに至りました。
不動産法務では、新たな制度を分析するに当たっても、歴史的経緯を踏まえた本質的な部分を元に検討することが不可欠です。当事務所は、古くから不動産分野に注力しており、その伝統と経験が蓄積されているとともに、事務所理念の一つである「複数の弁護士が協力して最高の質を有する法務サービスを提供すること」の実践として、培った伝統と経験を共有することを惜しまず案件に取り組んでいます。
かかる伝統と経験を元に本ニュースレターが読者の方々にとって有益となるよう発信してまいります。本ニュースレターにつき、ご感想のほか、忌憚のないご批判、ご意見も頂けますと幸いです。
不動産の証券化・流動化市場において、近時セキュリティ・トークン(又はデジタル証券)の発行案件は増加傾向にあり、これまでにも公募型のセキュリティ・トークン・オファリング(「STO」)が複数公表されているところです。不動産STOは個人投資家を対象とする小口化商品を不動産ファンドで実現することが可能となるものであり、またこれまで見られた個人投資家向けの不動産小口化商品とは異なり、セキュリティ・トークンという仕組みを用いることで流動性向上という差別化が期待できるものであるため、引き続き注目されている分野です。弊事務所においても不動産STO案件に複数関与しているところです。
本稿では、公募による不動産STO(「公募型不動産STO」)に焦点をあてて現状の実務の到達点を概観するとともに、今後注目すべき主要な論点をご紹介いたします。
セキュリティ・トークンは、あくまで、ある私法上の権利がブロックチェーン等の技術によりデジタルに管理される状態に置かれることでトークン化されたものに過ぎないため、セキュリティ・トークンの権利の発生要件、譲渡の有効要件及び対抗要件は、当該権利の私法上の取扱いによることとなります。
現在、公募型不動産STOにおいてトークン化される私法上の権利としては、受益証券発行信託の信託受益権が用いられています。受益証券発行信託の場合、受益証券を発行しない旨を信託契約において定めることで、当事者の合意のみによって受益権の譲渡が可能となり(信託法185条2項)、また受益権原簿への記載又は記録が受益者その他の第三者への対抗要件となります(信託法195条2項)。
かかる受益権原簿の管理についてブロックチェーン等の技術を用いてデジタルに行うことにより、私法上の取扱いにおいてもプラットフォーム内でSTOの権利移転及び対抗要件の具備をタイムラグが極力ない形で可能となる点にメリットがあります。
このようにタイムリーに権利移転及び対抗要件具備を行うことができることは、特に第三者との間での優先順位が問題となる差押※1や倒産時における取扱いにおいて重要な意味を持ちます。
一方で、通常多くの不動産私募ファンドで用いられる集団投資スキーム持分である、匿名組合出資持分は、匿名組合の根拠法である商法に譲渡の有効要件・第三者対抗要件に関する明文がないため、指名債権譲渡に準じて譲渡の有効要件・第三者対抗要件が取り扱われるのが一般的です。すなわち、譲渡の有効要件については、権利の移転の形で行う場合には譲渡禁止特約がある場合でも当事者の合意で譲渡可能ですが(民法466条2項)※2、匿名組合出資持分については権利だけでなく義務も負担する性質のものであるため、持分の譲渡は契約上の地位の移転という形で行われるのが通常であり、営業者の事前の同意が必要となります(民法539条の2)。また、第三者対抗要件を具備するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が民法上必要とされています(民法467条2項)。
このため匿名組合出資持分をトークン化している実例はございますが、匿名組合出資持分をトークン化した場合、第三者対抗要件具備のために確定日付のある証書による通知又は承諾が必要であるため、プラットフォーム内でデジタルに管理することが難しいという問題があり、かつ、トークン化された持分を取引した場合にそれに係る確定日付のある証書による通知又は承諾の取得に当たってはタイムラグも発生するため、第三者からの差押や倒産時における取扱い上の不都合が生じるおそれがあります※3。
上記のとおり、一定の権利の移転の第三者対抗要件の具備のためには、確定日付のある証書による必要がありますが、デジタル技術を用いた取引の活性化の観点から、第三者対抗要件もデジタル技術のみで具備できるように法改正がなされています。
具体的には、産業競争力強化法第11条の2において、認定新事業活動実施者によって認定新事業活動計画に従って提供される情報システムを利用した債権譲渡通知等については、確定日付のある証書によったものとみなす特例が認められました。
実証実験レベルでは、産業競争力強化法8条の2第1項に基づく新技術等実証計画として、当初SMS(ショート・メッセージ・サービス)を用いた1件が2020年6月26日に認定されていたところ※4、その後、SMSを用いた実証実験に係る事業者は、2022年4月27日に認定新事業活動実施者として認定されています※5。また、新たな新技術等実証計画として、2022年3月29日には、ブロックチェーンを用いた2件も信託受益権譲渡に関してではあるものの認定がなされています※6。
確定日付のある証書をSMSで代替させることはこれまでの確定日付の取得手間を省力化できる点で画期的であると評価できますし、さらにブロックチェーン型の技術が確立した場合には、匿名組合出資持分の権利の移転や受益証券発行信託以外の受益権の移転で問題となっていた確定日付のある証書の取得を行うことなくプラットフォーム内でデジタルに管理することが可能となるように思います。
不動産特定共同事業法(「不特法」)における不動産特定共同事業(第1号事業)を用いた不動産証券化・流動化スキーム(「不特法スキーム(第1号)」)に係る一定の任意組合出資持分や匿名組合出資持分は金融商品取引法上の有価証券である集団投資スキーム持分から除外されますが(金融商品取引法2条2項5号ハ)、不特法スキーム(第1号)に係る権利をセキュリティ・トークンとした場合についての権利関係や規制枠組については、不特法上手当がなされているわけではなく、今後の議論及び改正が待たれるところです。
次に資産の流動化に関する法律(「資産流動化法」)に基づく特定目的会社を用いた不動産証券化・流動化スキーム(いわゆるTMKスキーム)についてですが、優先出資の発行は登記(資産流動化法42条1項、2項)が必要であり、また、セカンダリーでの譲渡の有効要件として、優先出資証券の交付(同法44条3項)、対抗要件として優先出資社員名簿への記載・記録がそれぞれ必要となります(同法45条1項)。優先出資証券の交付は、指図による占有移転を用いることも考えられますが管理をどう行うべきかの問題が発生します。
匿名組合出資持分のように金融商品取引法2条2項各号に定める権利は従前二項有価証券と取り扱われていたところ、かかる権利が電磁的情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電磁的方法により記録されるものに限ります。)に表示される場合※7、「電子記録移転権利」に該当し、金商法の規定により別途除外されない限り、流通性の高い有価証券として金融商品取引法上一項有価証券と分類されることとなり、いわゆる証券会社による取扱いが必要となります。
このため、新たにセキュリティ・トークンを売買・預託する専業の証券会社(法2条8項16号)の設立も想定されるところです※8。
また、セカンダリー取引の場を提供する流れも考えられますが、金融商品取引法上予定されているプラットフォームについては①金融商品市場、②PTS業務、③OTC(店頭売買)業務の枠組の3種類が考えられます。しかし、①金融商品市場の免許のハードルは高く、②PTS業務のための第一種金融商品取引業の登録・PTS業務の認可や③OTC(店頭売買)業務のための第一種金融商品取引業の登録などは今後の進展を待つ必要があります。
なお、その他の金融商品取引法上の留意点として、顧客の関与なく、単独又は委託先と共同して、顧客のセキュリティ・トークンを移転することができ得るだけの秘密鍵を保有する等、主体的にセキュリティ・トークンの移転を行い得る状態にある場合には、基本的に、トークンの預託を受けたことになり(パブコメ回答160、161)、金融商品取引業に該当することとなりますので、ストラクチャーの検討に当たっては留意が必要となります。
個人投資家において、分離課税により特定の税率とされるのか総合課税として累進課税に服するのかは商品性に大きな影響があり、今後の税制の動向にも留意する必要があります。
不動産STOにおける議論が複雑化する原因の一つとして、投資対象となるセキュリティ・トークンの裏付けとなっている私法上の権利の譲渡の有効要件・対抗要件が根拠法毎に大きく異なることが挙げられます。ここからは立法論になりますが、近時デジタル化社会に向けた新しい金融商品の開発・市場の活性化に向けた議論が活発になっていることの関連で、これらの私法上の権利の譲渡の有効要件・対抗要件を大きく見直すことも必要となってくるのではないかと思います。少なくともセキュリティ・トークン化された証券についてはその裏付けとなる私法上の権利の法的性質にかかわらず、一律に譲渡(質権設定等なども含みます。)の有効要件・第三者対抗要件について規律する上書き立法があってもよいように思います。これに加え、差押手続などの民事執行・保全実務や倒産実務とも連続性のある形で法整備されることが望まれます。
セキュリティ・トークンは裏付け資産の有無や差異によって商品性が異なる以上、不動産STOの投資商品にも、暗号資産・NFT、ステーブルコインなどの他のデジタルアセットと異なる魅力があるはずであり、さらに発展するよう透明性の高い安全な制度設計がなされることが望まれます。
※1
なお、どのようなストラクチャーを用いたとしてもトークン化された権利の差押が執行裁判所においてどのように行われるかという論点自体は現状残っています。
※2
但し、譲渡禁止特約がある場合には、善意無重過失でない譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができます(譲渡禁止特約の債権効)。
※3
2021年10月29日トークン合同会社が提出した有価証券届出書によれば、匿名組合出資持分に係る第三者対抗要件の具備時期について、移転が有効となった日の翌営業日に証券会社が承諾書を作成し、当該承諾書に確定日付を取得する流れが想定されています。
※6
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/220329b_kouhyou.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/220329a_kouhyou.pdf
※7
ここにいう「表示される」の意味するところは、金融商品取引法等ガイドライン2-2-2及び金融庁「令和元年資金決済法等改正にかかる政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」(2020年4月3日公表)中の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(「パブコメ回答」)によれば、契約上又は実体上、発行者等が管理する権利者や権利数を電子的に記録した帳簿の書換え(財産的価値の移転)と権利の移転が一連として行われる場合には、対抗要件の具備まで求めることなく(パブコメ回答177)、基本的に、セキュリティ・トークンに該当することとされます(パブコメ回答174-176)。
※8
なお、既に自主規制機関として、日本STO協会が設立されています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


糸川貴視、北川貴広(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


遠藤努、中村日哉(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒、糸川貴視、大野一行(共著)
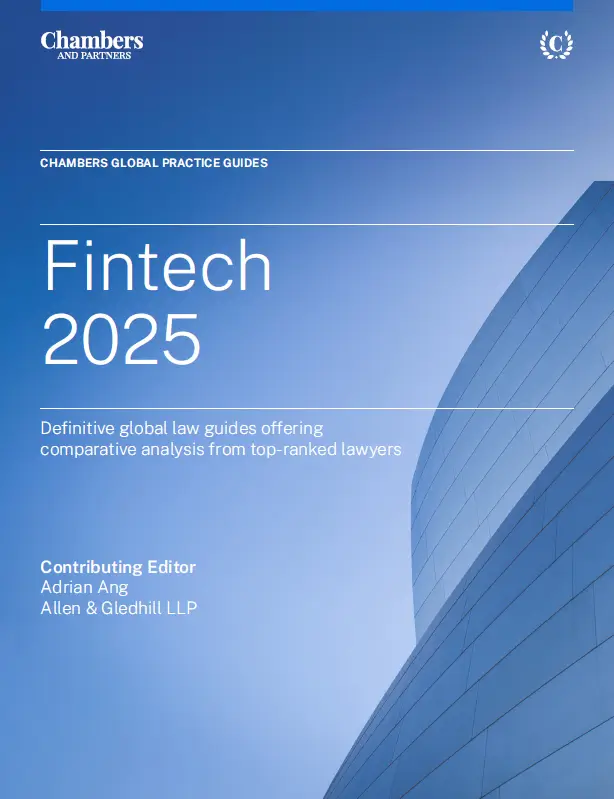
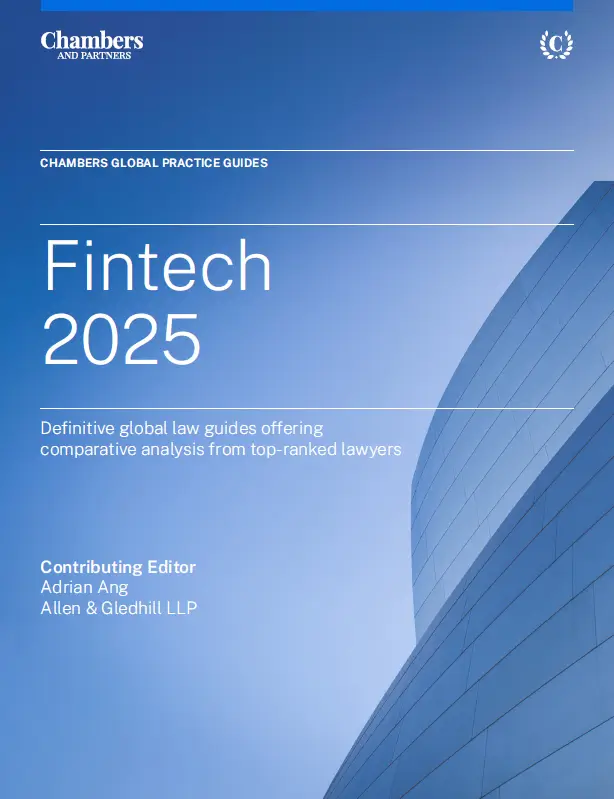
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)


(2024年12月)
清水音輝


(2025年5月)
井上聡、大野一行(座談会)


(2025年4月)
松本岳人


(2025年4月)
松本岳人


(2025年4月)
井上聡、大野一行(座談会)


遠藤努、中村日哉(共著)


(2025年6月)
水越恭平


(2025年6月)
吉良宣哉


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


(2025年5月)
吉良宣哉


(2025年5月)
井上聡、大野一行(座談会)