




【音声配信中】
プレイリストで聴取もできます。

医薬品、医療機器、再生医療、医療データ、デジタルヘルスその他広くライフサイエンス分野において、規制・コンプライアンスに関する助言のほか、M&A・提携、ライセンス契約、新規参入、資金調達等の事業活動全般にわたってアドバイスしている。

TMT分野を中心に、M&A、知財関連取引、テクノロジー関連法務、スタートアップ法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム、宇宙、個人情報・データ、AI、ガバナンス、ルールメイキングなど企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

コーポレート、不動産、紛争解決(仲裁・訴訟)を中心に企業法務全般を取り扱い、テクノロジー関連法務、スタートアップ法務及びメディア/エンタテインメント・スポーツ関連法務にも幅広い経験を有する。

ライフサイエンス・ヘルスケア分野を中心に、国内外を問わず、M&A、ライセンス、共同研究開発、データ関連取引その他の企業間・産学間の各種プロジェクト、並びに規制・官公庁対応等において、幅広くリーガルサービスを提供している。
近年のテクノロジーの発展とコロナ禍を経た社会情勢の大きな変化により、ヘルスケア・ライフサイエンス分野におけるテクノロジーの活用が加速しています。その中で、web3やメタバースといった新時代のテクノロジーについても、様々な場面で活用されることが期待されています。他方で、人の生命や健康を取り扱う分野であるがゆえに、複雑かつ厳格な規制が多く存在する領域でもあり、新たな取組みを行う際に検討すべき法的論点も多岐にわたります。今回は、web3・メタバース時代のヘルスケア・ライフサイエンスについて、ヘルスケア・ライフサイエンス領域の法務に多く携わる弁護士とテクノロジー領域の法務に多く携わる弁護士が議論します。

殿村

鳥巣

鈴木

殿村

鳥巣

小松

鈴木

小松

鳥巣

殿村



殿村

鳥巣

小松

鳥巣

殿村

鈴木

殿村

鳥巣

小松

鈴木

殿村

鳥巣


殿村

鳥巣

殿村

鈴木

小松

殿村

鈴木

鳥巣

鈴木

殿村

小松

鳥巣

殿村

鈴木



殿村

鳥巣

鈴木

小松

殿村

本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2023年3月)
鈴木謙輔
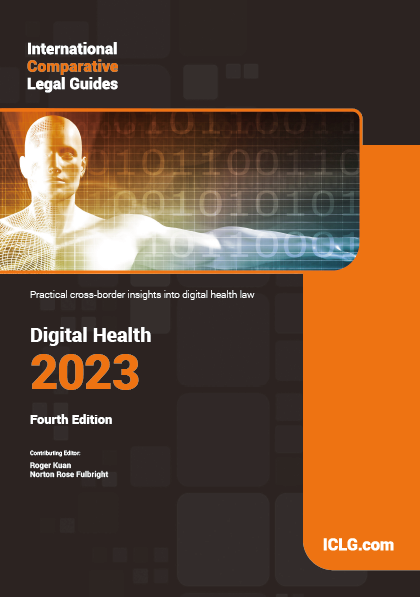
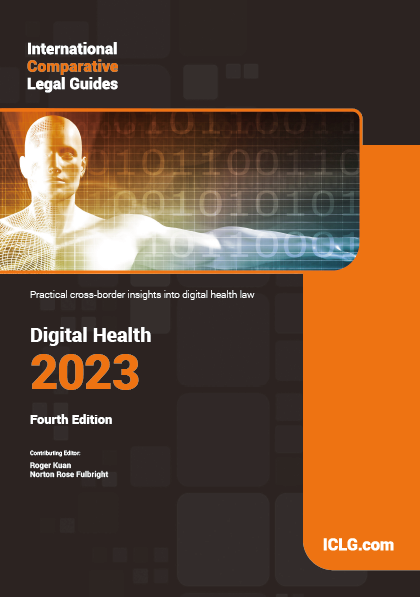
(2023年3月)
東崎賢治、鳥巣正憲(共著)


殿村桂司、近藤正篤、丸田颯人(共著)


殿村桂司、小松諒(共著)


殿村桂司、小松諒(共著)